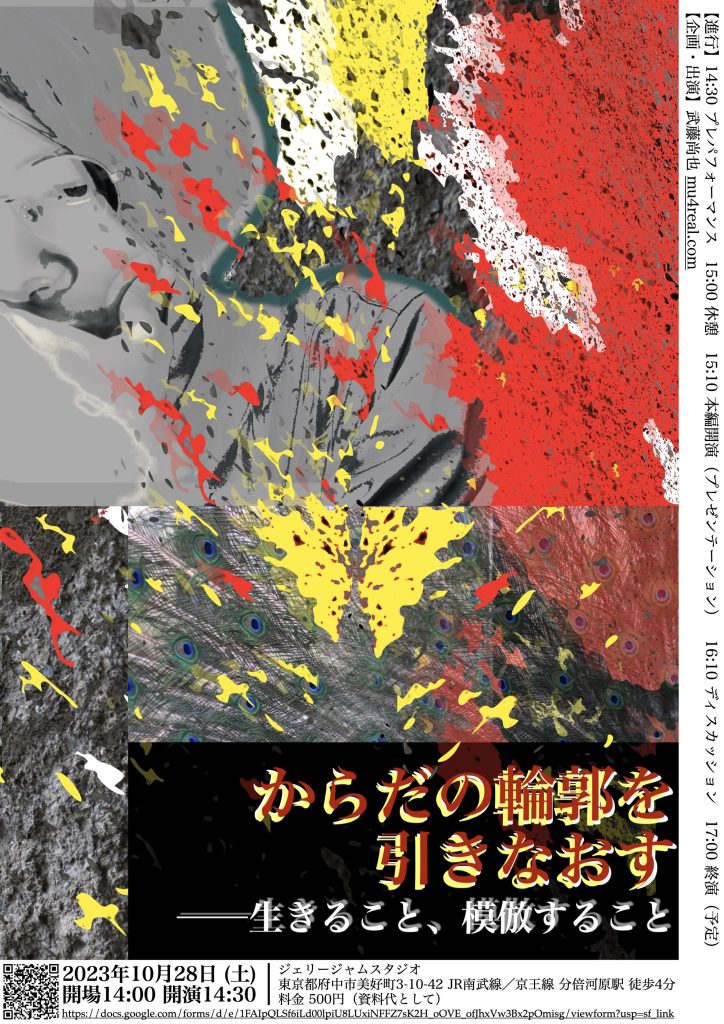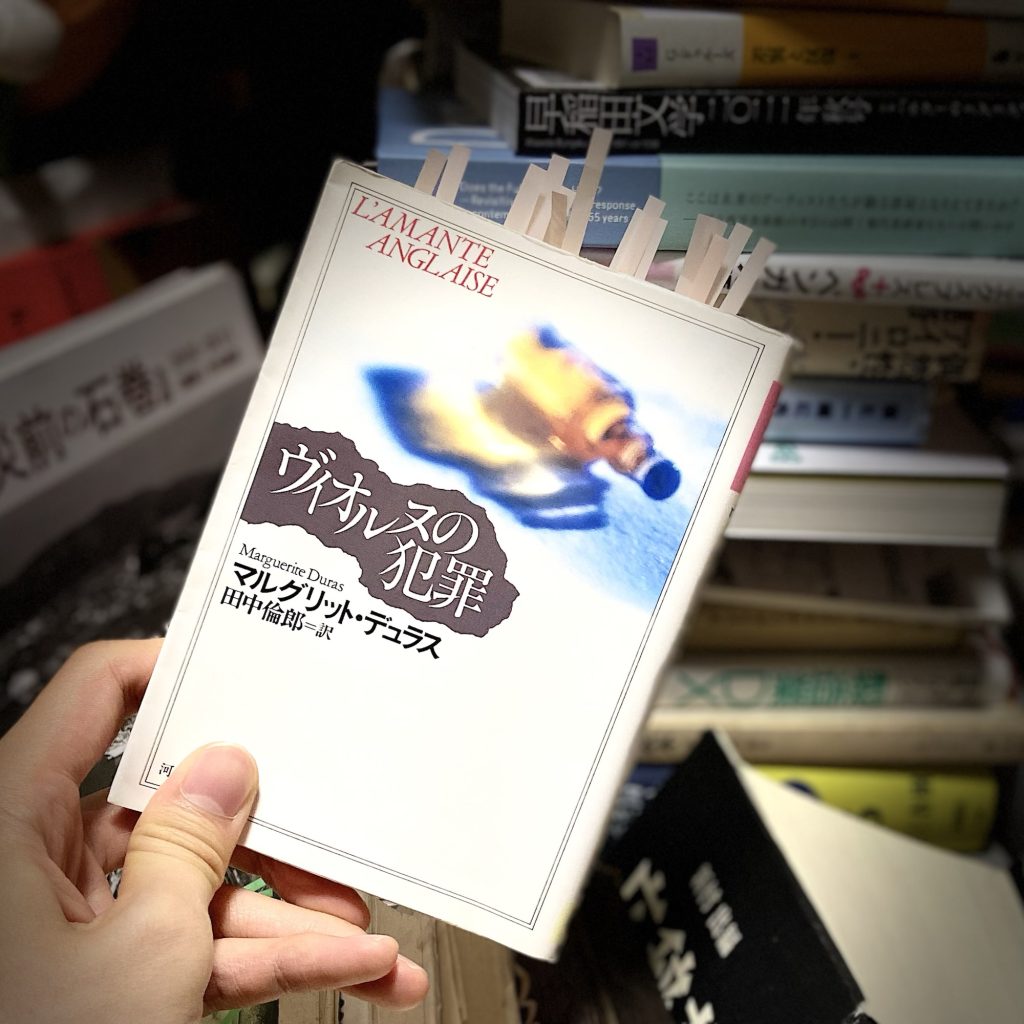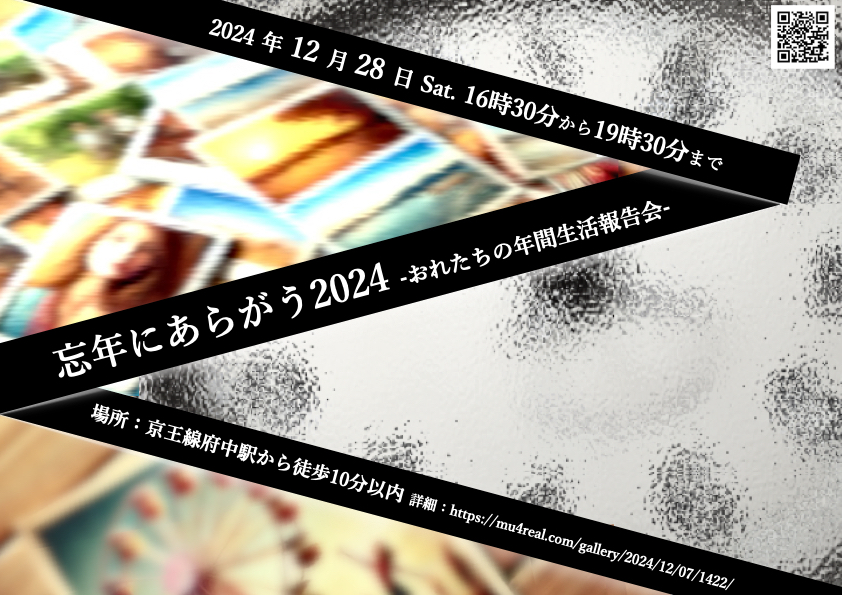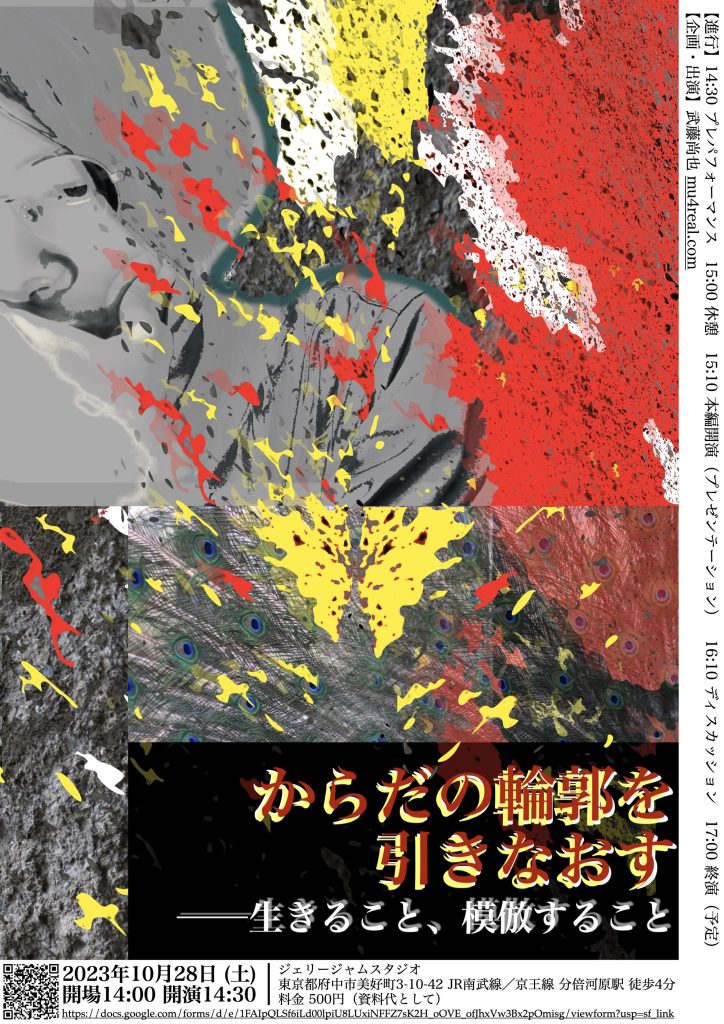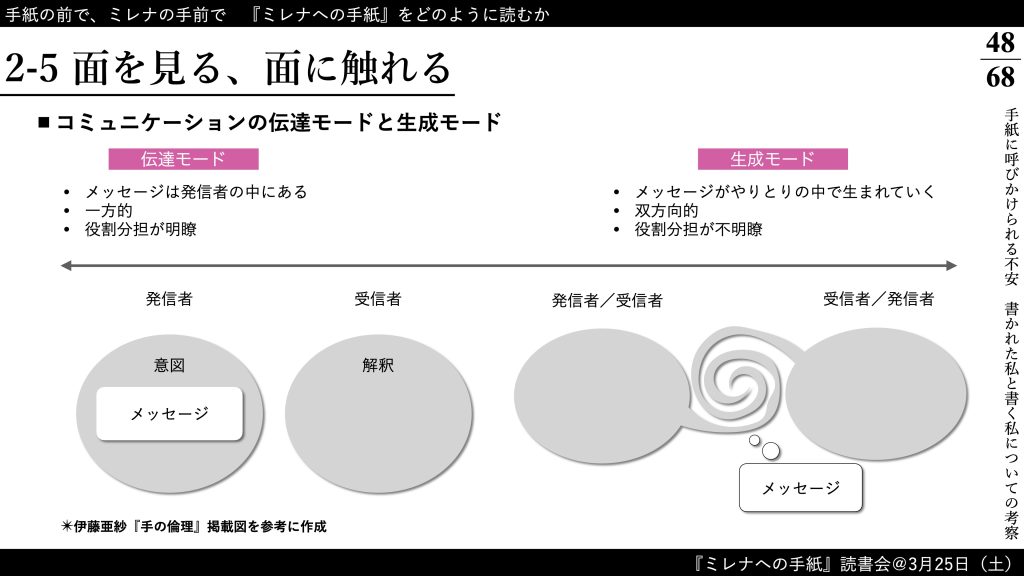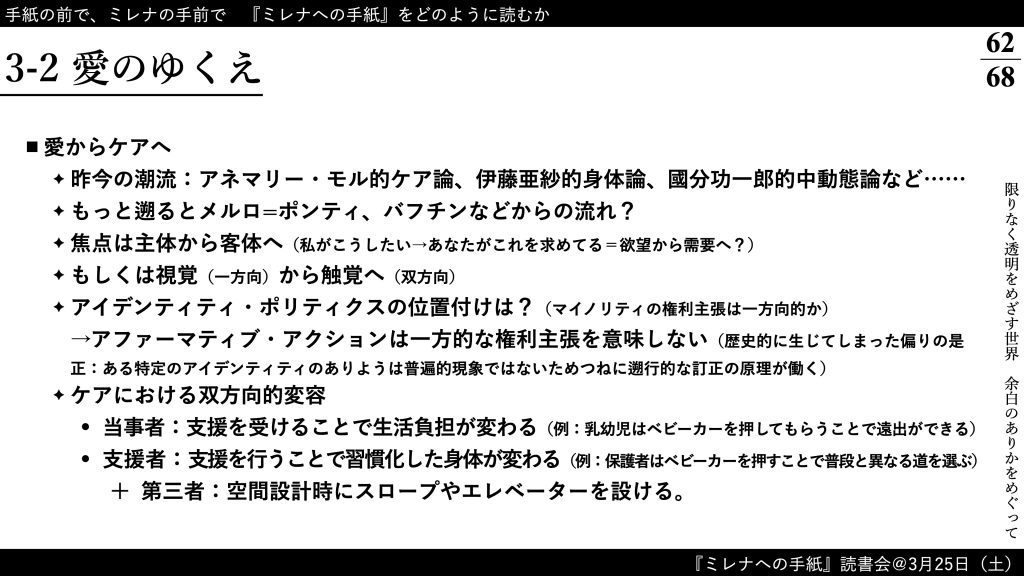どうしようと思ったときには心はいつもどうしようもなく
足りないということはかつて満ち足りていたものがあったという証左にほかならないのだが
いつも不在だけがその人の輪郭をかたどるように
いま私が手にしているものなど何もない
映画『おとぎ話みたい』(山戸結希監督)から筆者による書き起こし
かつて本をつくりました。『孤独な散歩者たちの夢想』と名づけました。本のつくりかたなんてわからなかったのでツイッターを介して協力を募りました。なんとなく見知ったひとやネット上でのみ存在を把握しているほぼ見知らぬひとなどがあつまり、ろくに本など読まずに20代そこそこまで過ごしてきた人間のひょんな思いつきによる制作物にしてはなかなかおもしろいのではと思えるものができあがりました。むろん、その成果はわたしの力によるものではなく、制作に協力してくれたデザイナーや参加してくれた寄稿者の方々のおかげであることは言うまでもありません。
この『孤独な散歩者たちの夢想』という本のあとがきでわたしはつぎのように書きました。
瞬間的でしかありえない私が有する偶然を足がかりに、何度となく私(たち)を部分的に死へと置き去りにする。切断された形跡が何重にも交差する地平で、同時に映写された複数のイメージに足を踏み入れる、多重化した主体を形成していく。そうした営みを成熟させていく場所を、技術を、策略を、方法論を、まだ持ちえていない段階において、まず取り組むべきだったこととして本誌を位置づけたい。
本という物体によって顕在化した理念性。外在化した私。世界に現れたこの新たな結節点に働きかけ(られ)ながら、わたしたちはネットワークをさらに拡充していくことができるはず。根拠なきわずかな希望を頼りに、制作の過程に生じたいくつもの連関を、制作物が引き継ぐ連関の広がりを、いつまでもどこまでも願いつづけてみようと思う。そして、脈々と拡張するその過程に、重厚な厚みを維持したままのわたしを埋め込む手立てを、しばしの間、もがきながら探ってみることにしよう。
むぅむぅ「あとがき」(『孤独な散歩者たちの夢想』)
恥を忍びながらに威勢よくじたばたしてみたところまではよかったけれど、宣言したとおりにその後ももがきつづけているかと問われるならば苦笑いを浮かべるのがせいいっぱい。いや正直に述べれば、この3年近くはなんとなくの生活に馴化して、波風が立たないように身のまわりだけは平凡に均しながら日々をひっそりやりすごしてきたように思います。
それもひとつの生き方でしょう。けれど、本棚に目をやると時折くだんの本が目について、ついつい手にとり卒業アルバムをめくるみたいな気分で読みふけってしまうのです。するとそこには上記のような威勢のよい死体が転がっているものですから、死の積みかさねを放棄したみずからの生がみっともなさをともなってぐわんと立ちあらわれてきては、均したはずの生活にまた波を立てられてしまうようなそわそわ感が全身を走りまわります。
そわそわをふりはらうかのように、このときのわたしはどこに向かって何を意気込んでいたのだろうと考えてみたりもします。
たとえばそんなに意気込んでいたのならまた本をつくろうとすることだってできたはずです。じっさい『孤独な散歩者たちの夢想』はわたしが企画した2作目の本で、本のつくりかたなんてわからないと泣きごとをいえる季節はもう過ぎた。けれどさてつぎはどんな本をつくろうかとはならなかった。むしろ当時のわたしは、たとえこれをこのままつづけたとしてもみずからの満足には到達できないだろうとすら考えていたはずです。
みょうにカッコをつけて無意味に観念的に書かれたあとがきですが、上記の引用文はひとことでいえば、あるていどまとまった量の文章を読み書きすることはおしゃべりをすることとは異なる性質のコミュニケーションとなるはずだ、と要約が可能です。そしてそのあるていどまとまった量の文章の交換によるコミュニケーションは世界から消えかかっている、少なくともじぶんのまわりにはない、このままではわたしがおもしろくないではないか!と主張したかったわけです。この主張があとがきという場面で記されていることは、こうしたわたしの欲望は当時の制作過程では満たされることがなく、また刊行後も満たされることはないだろうと予感していた点をあきらかにしています。
冒頭で記した制作経緯のとおり、この本の制作はほとんど見知らぬひとたちが突発的にあつまって行われた営みです。しかも文を読み書きする行為は基本的にはひとりで行うものですから、各自の作業は各自の範囲でのみ行われ、本としてまとめられるある段階でのみ集合し、本がそれぞれの手元に渡ったその瞬間に集団は解散され各自は散り散りになっていく。いっときのお祭りをたのしみたいだけだったらそれでも満足していたことでしょう。平凡なまいにちのちょっとした刺激として、ストレスフルな労働環境からの逃避先としてこの遊びをとらえるのであればじゅうぶんに効果を発揮していたことでしょう。ただ、お祭りを立ち上げていっときの盛りあがりを生んだとしても、携わったひとたちの生活それじたいが変わることはありません。元来はお祭りも町内で準備をする営みが日々の労働とはべつの層をなして生活に食い込んでいたのかもしれませんが、いまとなっては非日常に身をさらしては手軽に興奮や快楽を得るための装置としての側面ばかりを強調するのがものの例えとしての「お祭り的」というものです。
おしゃべりをすることとあるていどまとまった量の文章を読み書きすることとではコミュニケーションの性質が異なるはずだと直観したおおきな理由は、時間性のちがいという単純なものによります。一方でおしゃべりはその場で成されてその場で消える、他方で読み書きは行為に時間がかかるし書いたものものこりつづける。ではお祭りはどうでしょう。地元のひとたちにとって地元のお祭りは毎年つづくものであり1年にいちどの本番に向けた準備の営みは持続的ですが、お祭りを求めて外からやってくるお客さんはそのお祭りをその場かぎりのたのしみとして消費してはまたもとの日常にもどっていきます。むろん、外からやってくるお客さんがいなければお祭りはつづきませんが、わたしが複数名との本づくりを通じて試みたかったのはみょうちくりんだけど持続的なお祭り運営であって、労働とはべつのかたちで生活に横たわる制作の営みだったのでした。
結論として、孤独な散歩者たちはその孤独な道中でさほど交差をしなかった、といえるでしょう。それゆえ孤独であるのだから、書名の時点で答えは出ていたわけですが。
わたしはみずからの本の制作における意図と実態の乖離の原因のひとつとして自身の文字への過大評価という点を考えています。音声中心主義への抵抗としてエクリチュールの思想を掲げるのもけっこうですが、文字に偏ろうとするがあまり文字と音声の共犯関係を無視してしまってはただの逆張りにしかなりません。つまりほとんどSNSから生じた原動力だけで行われた制作の営みとその成果物にはひとのからだが欠如していたのではないか。ここに大きな反省があるのです。
そこでわたしは今年2023年に入ってから「文字は文字である以前にまず声であり、声はからだから発されるものである」ということを意識し、文字とからだを密着させられないかと試行錯誤するようになりました。また、2022年の夏ごろから体調がしゃっきりしない日が続いてどうにもならず2022年末に職を辞したということもあり、文字をつかって停滞したからだを再駆動させられないかということも思案していました。
いまだに続けているこの試行錯誤のなかで特に時間を割いているのが詩の朗読やラップの練習です。エドガー・A・ポーやパウル・ツェラン、萩原朔太郎や田村隆一など本棚にあった著名な詩人の詩集をてきとうに手にとって同じ詩を連日音読しました。また不可思議/wonderboyというラッパーが好きだったのでそのひとのラップをまいにち真似しました。さいしょは言い淀みのあった音読が、繰り返し繰り返し読み上げるなかで声の力点の置きどころがわかるようになり、言葉に口がついていけるようになり、2週間もすればすっかり暗記してしまいページを見ずとも一編の詩を朗読できるようになる。書かれた文字を読み上げるだけの行為から、ピアノを弾けるようになったり100メートル走のベストタイムをとつじょ大幅に更新したりといった例にみられる意識してもできなかった行為が無意識にできるようになっていく過程と近しいものを感じました。ピアノは高価だし置く場所もない、置けたとて近所迷惑になるから鳴らせない、じゃあ走る練習でもしようかと外へ出ても全力ダッシュが許される場所といったらみぢかには市営の陸上競技場くらいしかない。こうした環境の制約がわたしのからだをちぢませる。わたしのからだを硬直させる。わたしのからだに限界をあたえる。だけど文字はそこらじゅうに散らばっていて、わたしは文字を手繰ってからだに働きかけることができる。ちぢまったからだをまた押し拡げることができる。詩の朗読やラップの練習を経てその実感をつよくしたいま、文字はひとを自由にするのでは、とそんなことすら思えてきます。
他人が書いたテキストをわたしの声が再生する。はじめのころは発声行為に異和を覚える。それでも再生を繰り返すうちにわたしのからだがテキストになじんでいき、いつのまにかテキストの輪郭にわたしのからだはおさまってしまう。言葉がまず声であり声がからだから発されるものであるとするならば、それが文字であろうと声であろうと誰かと言葉を交わすことはからだを交わすことでもあり、じゅうぶんな肉体接触のあとではからだの変化は避けられない。
たとえばわたしはさきの本に載せた「孤独な散歩者たちの夢想 序説」という文章でつぎのように書いています。
あなたはあなたの境界を見失い、いくつもの文字列に取り込まれ、あなたでない誰かと一時的な同化を果たしたのちに、あなたへ回帰する。
むぅむぅ「孤独な散歩者たちの夢想 序説」
ひとはみずからのからだを単位として他者との境界をつくる。けれどわたしたちのからだは周囲から独立した自由なものとしてあるのではなく環境からの働きかけに押し出されるように言動や振る舞いを選択する。であるからこそワンルームのアパートではピアノを弾くなんてことはできない。同様にひととひとのコミュニケーションは周囲の環境をも含めたわたしたちの働きかけあいのなかで生じる。それ以前の積み上げを抱えるわたしとまた異なる積み上げを抱えるあなたが互いを押し合いへし合いすることで抱えている積み上げの構成が組みかえられる。あなたとの同期以前と以後とではわたしの姿がわずかなりとも変わってしまう。それが言葉を交わすということである。
この意味で、ひとは未完の草稿のようなものだと思います。他のテキストを参照しながら書かれたあるテキストは、何名ものひとに読まれ、それぞれ異なる解釈をされ、そのさまざまな解釈は新たに紙面に書き込まれる。新たな書き込みによってすでに書かれていたテキストの文脈は変わり、意味合いは変わり、書き直すことになる。その過程で参照テキストは増える。書きなおしを経たテキストはまた誰かに読まれる。この終わらない書きなおしの過程がひとが関わるということであり、ひとが生きるということなのではないか。
さて、10月28日に行う予定の集会「からだの輪郭を引きなおす──生きること、模倣すること」では上記したような制作行為(ひいてはコミュニケーション)のありようについて検討していく予定です。また検討のための素材として、今年から取り組みはじめた詩の朗読やラップの練習を中心にわたし自身の経歴を題材としてみていきます。
第一部ではおおげさな自己紹介という導入を経て、足場となりそうな理論の模索として東浩紀『訂正可能性の哲学』を出発点にウィトゲンシュタインやハンナ・アーレントが提唱した概念を確認します。また表現の分野からアントナン・アルトーを参照して手がかりをさぐります。
第二部ではわたしの関心から山戸結希、吉増剛造、円城塔といったジャンルもバラバラの作家を取り上げて各作家や作品の性質を実例として挙げながら制作の方法論になりえそうな要素を抽出します。
さいごにこの数ヶ月にわたる詩の朗読やラップの練習を経た実感をお話しします。
これらのプレゼンのまえにはプレパフォーマンスとしてじっさいにラップの上演を行う予定です。
基本的にはわたしがいつか誰かに話したかったけど話す機会もなければ誰も興味をもたなそうだしそもそもじぶんのなかでの詰めもあまいからとずっと胸のうちで抱えていたことをわたしが思うがままに話す場となります。上記した固有名詞もたんに好みから選ばれているだけでまったく脈略がなく、なんの歴史も背負っていません。もしかすると全編通しておおげさな自己紹介の域を超えることもないでしょう。けれどひとが全力で自己紹介をしたらきっとおもしろいはず、というむじゃきな期待を頼りにいろいろ準備に励んでいます。
あるいはこれは、けっきょくひとりで抱えていても議論は進展しないし新たな回路も開かれないし、というか頭もわるくてろくに学もなければ複雑なことなんてとうてい考えられないわたしでは手にあまることは目に見えているのだからともに考えてくれるひとを頼りたい!という助けを求める叫びのようなものなのかもしれません。
いずれにせよ、こういう機会があってもよいとおもえるかたや、こういう機会をおもしろがってくれるかたは、ぜひぜひお気軽にご参加いただけますとうれしいかぎりです。困ったことにひとが集まらないと開催できません。どうぞよろしくお願いいたします。
【タイトル】
からだの輪郭を引きなおす──生きること、模倣すること
【開催日】
10月28日(土)14:30〜17:00(終演時刻は予定。開場は14:00から)
【会場】
ジェリージャムスタジオ
東京都府中市美好町3-10-42
JR南武線/京王線 分倍河原駅から徒歩4分
【料金】
入場時に資料代として500円をお支払いいただきます。
※プレパフォーマンスのみご観覧の場合は無料です。
【進行予定】
14:00 開場
14:30 プレパフォーマンス
15:00 休憩
15:10 本編開演:プレゼンテーション
16:10 ディスカッション
17:00 終演
【申込方法】
以下のフォームからご申請いただくか、またはSNSのDMにて参加希望の旨をご連絡ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6iLd00lpiU8LUxiNFFZ7sK2H_oOVE_ofJhxVw3Bx2pOmisg/viewform?usp=sf_link
※プレパフォーマンスのみ観覧希望の場合はその旨をお知らせください。